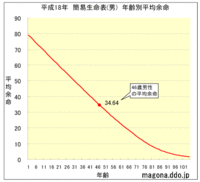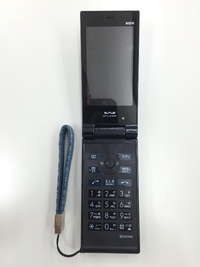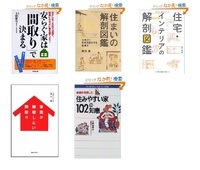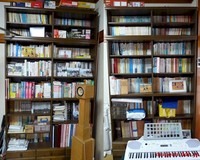2009年03月20日
ビデオ撮影の極意(バドミントン編)
先日、中学生になる娘のバドミントン大会に出かけた。当然のことだが、父親の役割はビデオ撮影である。体育館に到着すると、案の定、多くの父兄がビデオ撮影に取り組んでいる。しかし、残念なことに誰一人としてバドミントンの正しい撮影技術を習得しているようには見えない。全員がいい加減な角度から被写体を撮影していたのだ。中にはコート上を往復するシャトルを追いかけている方もいる。これでは、視聴者を船酔いに状態に陥れるブレブレ映像となるのは必至だ。できあがった映像について、子供の成長記録としての意義は否定しないが、競技力向上に資する試合記録としては今一歩と言わざるを得ない。
では、どうして正しいバドミントンの撮影方法を誰も知らないのか。理由は明白である。オリンピックでのオグシオやスエマエペアの大活躍により、バドミントンの認知度は確実に上がっているが、依然としてマイナー競技であることに変わりない。試合がテレビ放映される機会はゼロに近いといっても過言ではない。このため、ほとんどの父兄はバドミントンの試合放送を見たこともなく、どのように撮影すれば良いのか分からなかったのである。
しかし、ここで朗報だ。マゴナ研究室ではこれまでもビデオ撮影に関するさまざまなノウハウ(ビデオ撮影の極意①、②、③、④)を紹介してきたが、今回は、北京オリンピックや全日本総合選手権の映像分析により解明した「バドミントンの撮影の極意」を惜しげもなく公開したい。これにより、バドミントン部のご子息を持つ全てのご父兄が、競技力向上に資するバミントンの撮影技術をいとも簡単に会得できるのであった。裏を返せば、この撮影ノウハウは、いとも簡単に会得できるほど単純なのである。(笑)
 ここからが本題である。一般に、バドミントンの試合では、1階のアリーナ(競技場)に入れるのは競技者と審判だけである。したがって、父兄の撮影ポイントは2階観覧席に限定される。この時、最適な撮影ポイントは一カ所しかない。そのポイントは左図に示されるコートのセンターラインの延長線上である。この場所から、コートを見下ろす形で撮影するのだ。
ここからが本題である。一般に、バドミントンの試合では、1階のアリーナ(競技場)に入れるのは競技者と審判だけである。したがって、父兄の撮影ポイントは2階観覧席に限定される。この時、最適な撮影ポイントは一カ所しかない。そのポイントは左図に示されるコートのセンターラインの延長線上である。この場所から、コートを見下ろす形で撮影するのだ。
次に注意すべきは、コートをどのような構図で長方形のビデオ映像に収めるかである。これについてはコートから撮影ポイントまでの距離によって、二通りの方法が考えられる。
 まず、コートと撮影ポイントに一定の距離が確保され、コート全面がビデオ映像内に収まる場合である。この場合、左写真のように手前コートのエンドラインをビデオ映像の下限ギリギリに合わせ、コート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限に合うようにズームを調整する。この構図で画面を固定すると、選手がハイクリアー(いわゆる高い球)を打った時、シャトルが画面から一瞬消え、シャトルの落下途中で再び画面に現れるが、一時的なシャトル消失については何ら違和感なく試合進行を楽しむことができるので、ご安心いただきたい。逆に、シャトルの軌道が全て確認できるように広角で撮影すると、コート奧のプレーヤーが豆粒大となり、プレーの模様が全く確認できなくなってしまうので、これは避けなければならない。
まず、コートと撮影ポイントに一定の距離が確保され、コート全面がビデオ映像内に収まる場合である。この場合、左写真のように手前コートのエンドラインをビデオ映像の下限ギリギリに合わせ、コート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限に合うようにズームを調整する。この構図で画面を固定すると、選手がハイクリアー(いわゆる高い球)を打った時、シャトルが画面から一瞬消え、シャトルの落下途中で再び画面に現れるが、一時的なシャトル消失については何ら違和感なく試合進行を楽しむことができるので、ご安心いただきたい。逆に、シャトルの軌道が全て確認できるように広角で撮影すると、コート奧のプレーヤーが豆粒大となり、プレーの模様が全く確認できなくなってしまうので、これは避けなければならない。
 次は、不幸にもコートと撮影ポイントの距離が稼げずコート全面がビデオ映像内に収まらない場合である。この時は、左写真のようにコート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限を合わせ、手前コートの全てが映らなくても我慢するのだ。この構図では手前コートのプレーヤーがコート後方に移動すると画面から一時的に消えるが、それについては諦めるしかない。プレーヤーの動きに合わせてカメラを動かすと、画像はブレブレ映像になってしまい、見るに堪えないどころか、視聴者は強度の船酔い状態に陥ってしまう。不幸にもストレートで試合が決着しても、2ゲームのうち1回はご子息が正面を向いているシーンが残るので、特に問題ないと諦めるしかないのである。(笑)
次は、不幸にもコートと撮影ポイントの距離が稼げずコート全面がビデオ映像内に収まらない場合である。この時は、左写真のようにコート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限を合わせ、手前コートの全てが映らなくても我慢するのだ。この構図では手前コートのプレーヤーがコート後方に移動すると画面から一時的に消えるが、それについては諦めるしかない。プレーヤーの動きに合わせてカメラを動かすと、画像はブレブレ映像になってしまい、見るに堪えないどころか、視聴者は強度の船酔い状態に陥ってしまう。不幸にもストレートで試合が決着しても、2ゲームのうち1回はご子息が正面を向いているシーンが残るので、特に問題ないと諦めるしかないのである。(笑)
【閑話休題】
今回、娘が出場した大会は団体戦であった。試合は、第一ダブルス、シングルス、第二ダブルスの順番で進行し、勝ち数で勝敗を決する。原則、第一ダブルス、シングルスで連勝した場合は、第二ダブルスの試合はない。ただし、初戦だけはお情けで勝敗に関係なく第二ダブルスの試合が行われる。娘は第二ダブルスであったが、今回の大会では、ベスト16まで第一ダブルス、シングルスが連勝したために娘の出番は全く無かった。しかもベスト8を決める試合では、第一ダブルス、シングルスが連敗したために、結局、ビデオ撮影の機会は初戦だけとなり、筆者は体育館で無為な時間を過ごしたのであった。この間二日である。いくらバドミントン好きといっても、これではあまりにも退屈だ。この状況について、娘は「秘密兵器が秘密のまま終わった」と笑ったが、筆者は「秘密兵器」どころか「不発弾」に違いないと思うのであった。(笑)