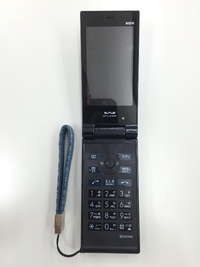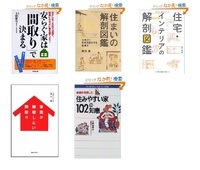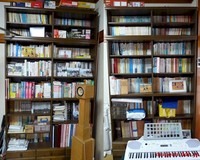2006年03月09日
壁紙の暴露試験
耐久性が求められる建築外装品や金属資材、塗料には、屋外での耐久試験が欠かせない。沖縄は、紫外線や潮風が強く、耐久試験場として最適である。沖縄本島北部地域の海岸沿いには、資材を屋外に長期間放置し経年劣化を観察する暴露(ばくろ)試験場を見ることができる。
暴露試験で得られたデータはメーカーの製品開発に活かされるが、一般には馴染みが薄い。ところが最近では、個人でCDやDVDメディアなどの身近な製品の暴露試験を実施し、耐久性をインターネットで公表するケースも増えてきた。当研究室においても、こうしたユーザー主導の時流に乗り、6年の歳月にかけた高温多湿の室内での壁紙暴露試験の結果を公表する(笑)。なお、以下で示す試験結果は、壁紙を自分で張り替えることを前提に記述しており、大工さんに張り替えを依頼する場合には全く無用の知識である。
壁紙は住宅本体と比べると経年劣化の激しいパーツである。およそ10年では、コンロの排出ガスやたばこの煙、湿気、ほこりなどによる「変色」、糊の劣化による「めくれ」が発生し張り替えが必要となる。壁紙張りは道具と根気さえあれば、ほとんど失敗しない簡単な作業であり、リフォーム本では作業手順を詳細に解説している。しかし、メーカーの陰謀かどうか知らないが、壁紙の耐久性に関する記述を見かけることはほとんどない。壁紙が消耗品である以上、耐久性はマイホームのランニングコストを左右する重要な要素であり、耐久性の高い壁紙を選択することは、設備投資を抑制する効果があると同時に、省資源、ゼロエミッションの観点から地球に優しい。
 試験結果を明らかにする前に、壁紙の種類について簡単におさらいする。壁紙は接着方法により次の4種類に分類される。
試験結果を明らかにする前に、壁紙の種類について簡単におさらいする。壁紙は接着方法により次の4種類に分類される。
①ノーマルタイプ:壁紙裏面に何のシカケもないタイプ。別途購入した糊をハケで壁紙裏面に塗布し壁に接着する。
②再湿タイプ:壁紙裏面にあらかじめ糊を塗布し乾燥させたタイプ、壁紙裏面を霧吹きなどで湿らせ、糊の接着力を回復させたうえで壁に接着する。
③生糊タイプ:壁紙裏面に生糊をあらかじめ塗布し、保護シートで生糊の乾燥を防ぐタイプ。保護シールをはがし壁に接着する。
④粘着タイプ:壁紙裏面が粘着シートになっているタイプ。保護シートをはがし壁に接着する。
 2000年5月の我が家のリフォーム時に、この4種類の壁紙をそれぞれ異なる部屋に張り、今日に至っている。経年変化の状況を観察したところ、「変色」はどのタイプにも認められない。しかし、粘着タイプは接着力が十分でないことから「めくれ」が目立つ。さらに「めくれ」部分にほこりが付着し、ますます「めくれ」が目立つ悪循環に陥っている。ノーマルタイプ、再湿タイプ、生糊タイプには「めくれ」の問題は生じていない。状況は壁紙のつなぎ目部分を拡大した写真(クリックで拡大)で確認できる。6年間に及ぶ壁紙暴露試験により、粘着タイプの耐久性が劣ることが明らかになった。
2000年5月の我が家のリフォーム時に、この4種類の壁紙をそれぞれ異なる部屋に張り、今日に至っている。経年変化の状況を観察したところ、「変色」はどのタイプにも認められない。しかし、粘着タイプは接着力が十分でないことから「めくれ」が目立つ。さらに「めくれ」部分にほこりが付着し、ますます「めくれ」が目立つ悪循環に陥っている。ノーマルタイプ、再湿タイプ、生糊タイプには「めくれ」の問題は生じていない。状況は壁紙のつなぎ目部分を拡大した写真(クリックで拡大)で確認できる。6年間に及ぶ壁紙暴露試験により、粘着タイプの耐久性が劣ることが明らかになった。
 4種類の壁紙は、価格、耐久性、準備作業、張り易さ、種類の豊富さで、それぞれ特徴がある。ちなみに「準備作業」とは、ハケによる糊の塗布や霧吹きによる糊の加湿作業、「張り易さ」とは、コーナーや出っ張り面などへの張り易さを意味している。筆者の主観に基づく総合評価を左表(クリックで拡大)に掲載した。お勧めは、ノーマルタイプ、再湿タイプ、生糊タイプ、粘着タイプの順である。ちなみに、プロは間違いなくノーマルタイプを使っている。一方、価格を気にせず、準備作業も楽に済ませたいという向きも多いと思われる。こういう要望には生糊タイプが適当だ。
4種類の壁紙は、価格、耐久性、準備作業、張り易さ、種類の豊富さで、それぞれ特徴がある。ちなみに「準備作業」とは、ハケによる糊の塗布や霧吹きによる糊の加湿作業、「張り易さ」とは、コーナーや出っ張り面などへの張り易さを意味している。筆者の主観に基づく総合評価を左表(クリックで拡大)に掲載した。お勧めは、ノーマルタイプ、再湿タイプ、生糊タイプ、粘着タイプの順である。ちなみに、プロは間違いなくノーマルタイプを使っている。一方、価格を気にせず、準備作業も楽に済ませたいという向きも多いと思われる。こういう要望には生糊タイプが適当だ。
今回の暴露試験に基づく耐久性評価は、試験回数(サンプル)が少ないことから、結果にバイアスがかかっている可能性を否定できない。しかし、情報が全く無いよりはよっぽどましだ。本試験結果を参考にするかどうかは、すべて貴方の勝手である。
【閑話休題】
壁紙の張り替え作業で重要なものは道具である。高いものではないので一通り揃えることが、美しい仕上がりを得るためには大切だ。特に、長いカット定規、コーナー用のカット定規は必須アイテムである。また、意外と重要なツールがカッターだ。刃をこまめに折りシャープな切れ味を維持することで、壁紙のつなぎ目が目立たないプロ並みの仕上がりが約束される。